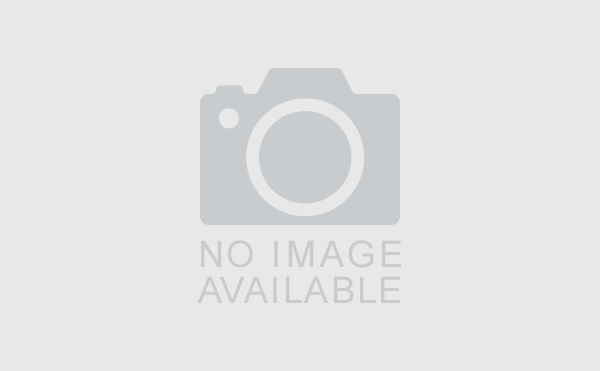東日本大震災から14年 災害対策に思う
東日本大震災から14年の年月が流れました。改めまして、亡くなられた方々に深く哀悼の意を表するとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみを申し上げます。そして、被災をされた方々に心よりお見舞いを申し上げます。
当社「ポジモ」はこの2年後に発売が開始され、一部の自治体では災害対策兼イベント用設備として活用していただいています。熊本地震の避難所でも活用され、北海道がブラックアウトした胆振東部地震では厚真町の避難所で活用されました。厚真町の避難所では余震のたびにポジモへの接続数、トラフィックともに急上昇して、避難所の方々の心細さと通信需要を痛感いたしました。
地震発生直後の避難所のFree Wi-Fiをポジモで
https://www.poggimo.info/blog/2022/11/474/
被災直後の通信確保の必然性は、これらの私たちの体験からも明らかになっています。能登半島地震では衛星インターネットStarlinkを外部から持ち込んで活用されるなど、14年前と比べると被災時の通信復旧の選択肢は拡がってきている印象です。私たちも、下記のようにStarlinkとポジモを組み合わせた活用を実証しています。
衛星インターネットをポジモで活用してみた(前編)
https://www.poggimo.info/blog/2023/07/657/
このように被災後の通信確保が非常に重要であるのですが、まだその確保手段については模索が続いているのかもしれません。防災庁設置準備アドバイザー会議の第1回議事要旨ではネットワークに関しては「日本の機関は、東日本大震災等の自然災害の際にもダウンしなかった大規模ネットワークを実現する技術を持っており、デジタルは防災分野に大いに貢献できる。」とコメントがあったのみです。
防災庁設置準備アドバイザー会議
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bousaichou_preparation/index.html
一方でインターネットの情報を収集してみると「災害直後の通信の確保」というテーマに対して
- 地域の防災計画に通信対策を組み込む
- 自治体と通信会社が連携し、災害時の通信確保の計画を立てる
- 衛星インターネット(Starlinkなど)を導入する自治体も増えている
というサマリがあり、先進的な自治体などでは「発災直後の通信手段確保」を促進していることが分かります。様態としては「外部との連携」「内部保有機材の活用」となるのだと思います。
ポジモやStarlinkなど内部保有機材を被災時に活用するためには、平時の活用でノウハウを磨いておく、そのノウハウを他の人に繋いでいくと言った準備が必要になります。私たちはこういった準備に真剣に取り組み、確かな技術・ノウハウで災害時に皆様を支援できるように、各方面に働きかけながら災害対策を推進していきます。